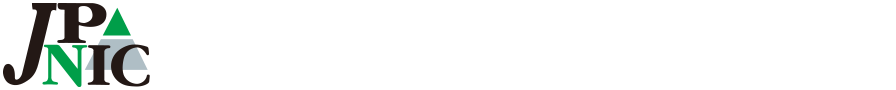ニュースレターNo.79/2021年11月発行
傾きの心に魅せられて
JPNIC評議委員 金子 康行
いきなり個人的な話で恐縮だが、私は歌舞伎ファンである。 初めて歌舞伎を観たのは大学生になった1990年頃だと思うが、 具体的なことはよく覚えていない。 その後も断続的に歌舞伎を観ていたが、 本格的にはまったのは歌舞伎座の建て替えが始まる2010年頃からだ。
私にとって歌舞伎鑑賞は、間違いなく生涯の趣味になるだろう。 ロングランを基本とするがゆえに、同じ演目をさまざまな役者が演じる、 その個性の違いの面白さ。 歌舞伎役者が文字通りその生涯をかけて芸道に精進し、 挑戦と成長を経て芸を継承し、 また次の世代へとバトンを受け渡してゆくさまを同時代に目撃する高揚感。 一生飽きずに観続けられるだけの楽しみが、そこにはある。
歌舞伎の素晴らしさは、なんと言ってもその世界の広さと深さにある。 歌舞伎という漢字表記はいわゆる当て字だが、歌=音楽性、舞=舞踊性、 伎=役者の技芸、とは、誠に的を射たうまい表現である。 歌舞伎と言われて多くの人が思い浮かべるであろう「隈取」「見得」「ツケ」といった、 独特の表現方法をもった演劇、というだけでは、 到底その全体像を説明できているとは言い難い。
演劇としての脚本の妙や役者の存在感はもちろん、音楽、舞踊、衣装、舞台装置、 それぞれが独立した芸能・芸術として成り立つだけの深みを持ち合わせながら、 それらを同じ板の上にこれでもかと並べて、 観客の五感をライブで贅沢に楽しませる総合エンターテインメント、 とでも言えば少しは伝わるだろうか。
歌舞伎を観るにあたって、必ずしも詳しい知識が必要というわけではない。 ふわっと舞台を観て、「ああ、きれいだな」とか、「理屈抜きにかっこいいな」とか、 「なんだか滑稽で笑えるな」とか、単純にそう感じられればそれでよい。 だが、より詳しく知りたいと思えば、そこからいくらでも深く入り込んでゆける。 たとえば音楽なら、主なジャンルだけでも長唄、竹本、常磐津、清元があり、 演目によっては大薩摩や河東といったものも使われるし、 囃子方(笛、小鼓、大鼓、太鼓)の存在も欠かせない。 それぞれの違いや特色、歴史、演者の個性などがわかってくると、 また俄然面白くなってくる。
歌舞伎の始祖は400年ほど前に現れた、 出雲の阿国と称する女性芸能者とされている。 彼女が京で披露した「かぶき踊り」は、 男装した阿国と女装した男がエロティックに戯れるという倒錯的な内容で、 その常軌を逸した先端性と斬新な美学=「傾き(かぶき)」が大衆を熱狂に陥れた。 その後、歌舞伎がもつ猥雑さや社会批判精神は風紀を乱す元凶であるとして、 たびたび時の権力者から規制と弾圧を受けることとなるのだが、 踏まれるほどに立ち上がる雑草のように、 しなやかな変化と大衆の支持によって現代までしたたかに生き残ってきた。
歌舞伎はとかく貪欲で、他の芸能を自らに取り込む力に長けている。 能狂言、人形浄瑠璃、落語など、流行した芸能を丸呑みし、歌舞伎風に消化して、 自家薬籠中のものとした。 近年では漫画・アニメ、ボーカロイドといったものまで歌舞伎に取り込まれている。 2019年12月に上演された「新作歌舞伎 風の谷のナウシカ」は、 完全に宮崎駿のナウシカの世界であり、また完全に歌舞伎でもあった。 あるいは初音ミクと中村獅童が共演する「超歌舞伎」は、 2016年に幕張メッセで開催されたイベントの数日限定の演し物として作られたが、 その後毎年恒例となり、 ついには2019年8月と2021年9月に正式な歌舞伎公演として京都南座で上演されている。
歌舞伎は「伝統」芸能ではあっても「古典」芸能ではない、 と喝破した役者が誰であったかは忘れたが、 実際に現代でも歌舞伎の新しい試みは絶えず、とてもここには書ききれない。 その上、商業演劇としても立派に成立し続けているのだから、 「古典」というレッテルに反発を感じるのも道理であろう。
さて、歌舞伎について長々と語ってしまったが、 私はインターネットももちろん大好きで、 しかも歌舞伎とインターネットはどうにも似ているような気がしている。
私がインターネットを触り始めた頃は、 電話回線を使ってインターネットに接続していたが、 あっという間にインターネットを使って電話サービスを利用するという逆転現象が起こった。 ラジオもテレビも、新聞も雑誌も、お店もゲームセンターも学校も職場も、 気がつけば生活のあらゆる要素がインターネットの世界に飲み込まれた。
インターネットは単にデバイスやアプリケーションをつなげるだけでなく、 人間の思考と行動と文化をつないだ。 それによって(やや誇張気味な表現かもしれないが)、世界の秩序を揺るがし、 混沌を巻き起こし、対立と和解を繰り返しながら発展してきた。 そもそもインターネットには、プラグマティックでラディカルな文化的背景がある。 それはまさに「傾き(かぶき)」の精神と相通ずるものだ。 私を含む多くの人がインターネットに魅せられたのも、むべなるかなである。
「わが血はかぎりなく古く また常に新しい」(ヴ王「風の谷のナウシカ」)

株式会社グローバルネットコア 常務取締役。 大学生の頃に初めてインターネットに触れる。 都内企業に就職後、1997年にISP事業を立ち上げ。 事業管理、商品開発、技術運用などを担当。 2004年に出身地である新潟に戻り、現在の所属企業でISP、 ホスティング、データセンターなどの事業推進に従事。 2010年に越後ネットワーク・オペレーターズ・グループ(ENOG)を設立。 2012年から2020年までJANOG運営委員。 2016年からJPNIC評議委員。