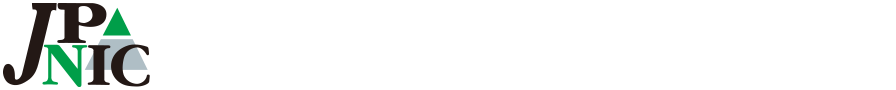ニュースレターNo.88/2024年11月発行
インターネットとイノベーション推進
NTTコミュニケーションズ株式会社 執行役員 イノベーションセンター長
友近 剛史
私は今年初めてJPNICの理事を拝命しまして(よろしくお願いいたします)、 JPNIC Newsletterの巻頭言を書くにあたり、 JPNICがインターネットの中核的なインフラを支える責任を担っていることを改めて認識しています。 言うまでもなくインターネットは我々の生活を豊かにしてくれるだけでなく、 昨今の国際情勢における情報発信の重要性の高まりやリモートワークの定着を背景に、 必要不可欠な社会基盤となっています。
私は1995年4月にNTTに入社し、 1996年12月のOCN(というISP)の立ち上げに従事しまして、その際、 OCNバックボーン網のルーティング設計開発を担当しました。 OCNサービス開始後も、 当時はバックボーンルータ運用に特化した部署は存在しなかったため、 開発担当の私が運用も担当していました。 バックボーン運用エンジニアとして担当したよくある業務としては、 IX等でBGPを使ってpeeringしている相手ASとのAS-PATHフィルタのアップデートがありました。 その際、それを実際のBGP経路送受信に反映するためにはBGPセッションをリセットする必要があるのですが、 「clear ip bgp *」という、 とある有名ルータでのコマンドを打っていました。 1日2、3回くらいやっていた感覚です。 このコマンドはBGPのTCPコネクション自体を切断する方法で、 BGPのダウンが発生し、 経路を読み込むまで通信断(経路によりますがだいたい数十秒)が伴います。 しかも「*」というのは、 すべてのBGP peerが切断される(IXでのpeeringの相手ASが100あれば、 100個のBGP peer全部が切断される)コマンドになります。 当時はsoft reconfigurationがなかった等の理由があったものの、 今思うとこんなことが許されていたのか、 と隔世の感があります。
昔話はこのくらいにして、 現在のインターネットを取り巻く環境は日々目まぐるしく変化しています。 私はイノベーションの推進を担当しておりますが、AI、IoT、 ブロックチェーン、フィンテックといった技術革新が私たちの社会に大きな変化をもたらしているような現状を鑑みるにつけ、 イノベーション推進の重要性を強く実感しております。
イノベーションは企業にとっては未来を切り拓く鍵であり、 成長の原動力です。 ご存じの方も多いと思いますが、 イノベーションを企業で推進するためには「両利きの経営」の実践が重要と言われています。 これは「知の深化」(=既存事業の絶え間ない改善)と、 「知の探索」(=将来の新規事業に向けた最先端の取り組み)を両立させることで、 変化の激しい現代でも「イノベーションのジレンマ」に陥らずに長期的に競争優位性を維持・向上し、 持続的成長ができる、という理論です。 「知の深化」だけでなく、 バランスよく「知の探索」も実行することが重要ということがポイントです。
「知の探索」を実行する際に重要なことはいろいろありますが、 特に以下の5点が重要だと考えており、 私が担当するNTTコミュニケーションズイノベーションセンターでも取り組んでいます。
一つ目はイノベーション文化の醸成です。 これは失敗を恐れずに新しいことにスピーディに取り組むことができる環境を整えることです。 そのためにはオープンで風通しのよい組織作りが必須だと思っており、 そういう取り組みをしています。
二つ目は顧客視点で考えることです。 ニーズを理解し、顧客が本当に求めている価値を提供する視点です。 そのために、組織として先端技術だけでなくビジネスデザインの専門家も多く持つようにしています。
三つ目は「知の探索」が「知の深化」と分断しないようにすることです。 とらわれ過ぎてはいけませんが、 既存事業や自社の強み・ケイパビリティ(能力)を意識することは重要です。
四つ目は新しいことを常に学習しようとする好奇心です。 新技術はもちろんですが、 市場・顧客の動向をアンテナ高く学習し続けることです。 組織としては、 新しい知識や発見をお互いに共有するようにしています。
五つ目は一つ目と重なるところもありますが「まずは実行してみる」という組織風土です。 そのためには、さまざまな枠を超える必要があります。 私たちの組織の行動指針(Value)として「未来を見せる」「枠を超える」「Implement First」の三つを規定しています。
最後に、JPNI Cの新任理事としては、 インターネットの健全な発展に貢献してまいりたいと思います。 上記でインターネットを取り巻く目まぐるしい変化と述べましたが、 これはいいことだけでなく、 サイバーセキュリティの脅威の深刻化など、 新たな課題も浮き彫りになっています。 NTTコミュニケーションズ イノベーションセンターでも、 RPKIの実証実験や、 DDoSインフラの内部構造に踏み込んだ攻撃の早期検知等に取り組んでいますが、 引き続き安心・安全で快適・便利なインターネットを目指し続けたいと思います。 JPNICの活動は日本のインターネットの発展に直結するものと思いますので、 今後とも、JPNICの活動にご理解、ご支援を賜りますよう、 心よりお願い申し上げます。

1995年、東京大学大学院電子工学専攻修士課程修了。 同年、日本電信電話株式会社入社後、 1996年12月サービス開始のOCNの立ち上げに従事、 OCNバックボーン網のルーティング設計開発を担当。 1999年のNTT再編時にNTTコミュニケーションズに配属され、 カーネギーメロン大学留学を経て、 課長・部長時代にOCN等へのIPv6導入を推進。 その後、クラウド開発担当部長、システム開発部門長、 NTT持株会社にて技術革新推進室長を歴任。 2023年より現職。 「インターネットルーティング入門」第1~3版執筆。