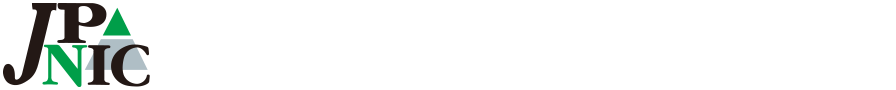ニュースレターNo.88/2024年11月発行
JPNIC会員と語る

「JPNIC会員と語る」は、JPNIC会員の興味深い事業内容・ サービス・人物などを紹介しつつ、 JPNICの取り組みや業界が抱える課題や展望などについての、 対話の模様をお伝えするコーナーです。
今回は、1965年6月に創業し今年で60年目を迎える、 株式会社両備システムズを取材しました。 同社は現在では親会社となっている当時の両備バスの電算部門が独立する形でスタートし、 その後事業範囲を拡大していく中でインターネット関連事業にも進出。 今ではさまざまなレイヤにまたがる形で幅広いサービスを展開しています。
今回の取材では新しく綺麗な岡山本社のオフィスを訪問し、 公共系の事業で圧倒的なシェアを持つ同社の強みや、 人材育成に関する考え方、 また岡山だけでなく東京でも多くの事業を行っている同社から見た、 地域格差に関する課題や原因、 JPNICに期待することなどについて幅広いお話をすることができました。

~公共部門で選ばれ続ける実力を民間向けサービスでも~

株式会社両備システムズ
| 住所 | 〒700-8508 岡山県 岡山市 北区 下石井2-10-12 杜の街グレースオフィススクエア 4階 |
| 設立 | 1965年6月5日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松田 敏之 |
| 従業員数 | 1,584名(2024年10月時点) |
| URL | https://www.ryobi.co.jp/ |
| 事業内容 |
https://service.ryobi.co.jp/
▶ 公共、医療、社会保障分野および民間企業向けの情報サービスの提供 ▶ ソフトウェア開発 ▶ ネットワーク構築サービス ▶ クラウドサービス事業 ▶ ハードウェア販売および保守サービス ▶ データセンター事業 ▶ セキュリティ事業 等 |
幅広いラインナップからベストな組み合わせを選んで提案できる強み

▶ まずは貴社の成り立ちを伺ってもよろしいでしょうか。
小西:元々は両備バス株式会社(当時、 現:両備ホールディングス株式会社)から独立する形で、 協同組合岡山電子計算センターが1965年6月に設立されたのが当社の始まりで、 1969年12月に株式会社として改組・設立されました。 設立当初は、 ホストコンピュータを使った受託計算が主な業務でしたがそこから業務を拡大していき、 1973年に現社名へ変更して現在に至ります。 組織的には2020年に他の両備システムズグループ5社と合併したことで、社員数は倍以上になりました。
データセンター事業への参入は、 2000年初頭のデータセンター(DC)構築ブームの頃で、 私どもも自社のDCをということで、 国道2号線沿いにあった今の岡山本店のホストルームを改装する形でDCを開設しました。 ただ、インターネットデータセンターとしては、IX(Internet Exchange)までの遅延時間などの問題から地方でのDC需要は大きくはなく、 自然災害が少ないエリアであることや家賃が安くフロアスペースの効率化の必要がないことなどから、 オンプレミスからDCに設備を移そうという地元のお客様も多くはありませんでした。 そのため、 自社のSaaSやASPのサービス発信の基盤としての使い方が中心でした。 転機となったのは2011年の東日本大震災で、 それまでほとんどお話のなかった関東・関西のお客様からの直接のお問い合わせをいただいたり、 バックアップサイトとしての案件をいただいたりするようになりました。 また、地元のお客様やSaaS・ASPをご利用のお客様からも立地やDC専用として作られた建物ではないことに対するご指摘をいただいたこともあり、 最初から専用に立てられたDCを新たに作りました。 その後もお客様が増え手狭になるごとに新DCを開設していった結果、 最新のRyobi-IDC 第3センターが2020年に竣工しています。
▶ 事業の主力は公共向けと伺っています。 割合としてはどのような感じなのでしょうか。
小西:全社の売り上げで言うと、 自治体向けと医療向けを合わせた公共系で全体の3/4ぐらいを占めています。
元々当社が富士通製コンピュータの販売店をしていた関係から、 病院向けのホストコンピュータの共同利用サービスを提供するようになりました。 医療の分野でのこういったサービスは当社が日本初と聞いており、 その後電子カルテなどへと取り扱う範囲が広がっていきました。 また、 1990年代に住民基本台帳ネットワークシステムを自治体向けに納入する仕事を受けるようになり、 それがきっかけでいろいろな自治体の仕事も受けるようになりました。 当時は自治体自身がホストコンピュータを置いて、 印刷なども自前でやるのが当たり前で、 大手事業者は国向けのサービスはやっていましたが自治体向けはやっていなかったこともあり、 当社がシェアを増やしていきました。
▶ なるほど、先駆者としての強みがあるわけですね。 それ以外に、 貴社の強みはどのようなところにあるとお考えでしょうか?
小山:当社のような地域のDC事業者やネットワーク事業者は、 アプリケーション開発から始まっているところが多いですね。 そのため、 DCやネットワークだけではなくアプリケーションも扱っていて、 東京の事業者などと比べてサービスのラインナップが多いことが特徴です。
小西:当社の強みはそういった幅広いラインナップを持っていることで、 いろいろなサービスやソリューションを組み合わせて提供することができる総合力です。 そういった部分を今後も高めていくことで、 他社との差別化を図っていきたいと考えています。 具体的には、アプリケーションだけではなく、 その下にあるアプリケーションが利用するネットワークやSaaSが置かれているDCなど、 それらを統合してお客様にベストなものを提供できるようにしていこうと考えています。 その観点で、インターネットやクラウドへのコネクティビティなど、 ネットワークの重要性はますます高まってきています。 新規需要の創出やさらなる海外進出なども視野に入れつつ、 2030年度に売上高500億円をめざす中期経営計画を実行しているところです。
▶ 貴社の東京本社を拝見したことがあり、 和のイメージを取り入れるなどとてもおしゃれだなと思いましたが、 本日伺っている岡山本社もとてもセンスがよく、 働きやすそうなオフィスですよね。 オフィスには力を入れてらっしゃるのでしょうか。
小西:採用に関して、 応募者の会社選択時の関心にオフィス環境の善し悪しが入ってきています。 また、若い世代のエンゲージメントを上げたいということで、 当社としてはかなり費用をかけています。 この岡山本社のオフィスは出社率70%を基準に、 みんなが来たくなるようなオフィスをめざして作られています。 以前本社があり今は本店となっている豊成オフィスではみんな車通勤だったので、 公共交通機関の利用が前提となる新オフィスに移転した際は離職者を心配していましたが、 幸い杞憂に終わっています。 岡山と東京の行き来は頻繁にあり、 案件の数的に岡山にいながら東京の仕事をしているということも多いですね。
▶ フリーアドレスでカフェ的なスペース、 リラックススペースがあるのはもちろん、 自由に移動できるようにモバイルバッテリーのステーションなどもあってびっくりしました。 社員の方が働く環境をしっかり考えられていますよね。
小山:岡山本社オフィスにはいろいろな新しい試みが導入されています。 もちろん、中には成功したものと失敗したものがあり、 それを踏まえより洗練し構成したものが東京本社オフィスとなります。 他社さんのオフィススペースの中には、 フロア内で階を繋ぐ階段やいつでもワンコインで飲食が可能なスタンドがあるなどさらに進んだところがあります。 オフィスの作りは社内の円滑なコミュニケーションに繋がりますので、 とても重要と考えます。
東京一極集中の現状が抱える課題

▶ 環境作りから取り組むなど、 採用にとても力を入れてらっしゃるということがよくわかりました。 リモート勤務の普及で東京と地域の垣根が低くなったという声もあるのですが、 採用活動に何か変化はありましたでしょうか。
小山:はい、垣根は確かに低くなりましたが、 いいことばかりではありません。 これまでは岡山に住みたければ岡山で働くしかなかったのですが、 リモート勤務の普及で岡山に住みながら東京の企業で働けるようになりました。 また、東京で働いていても、 本人の希望に応じていざという時には地元に転勤できる制度を導入する東京の大手事業者も出てきて、 当社のような地域のベンダーにとっては、 コロナ禍はむしろ逆風になっている側面もあります。
小西:フルリモート勤務を条件に東京の事業者が地域の中核都市の人員をヘッドハントし、 中核都市の事業者がさらに人口の少ない地域からヘッドハントするということが発生しています。 また、昔と比べると安定志向が強くなっているのか、 大企業を希望する若い人が増えている印象ですね。 社員数も就職先の評価基準にされてしまうので、 それでグループ6社が合併したという部分もあります。
また採用だけではなく、どんな仕事でもそうだと思いますが、 この業界も世代交代が課題になっています。 もう今と昔では、育った土壌が違いますからね。 我々が育った頃はトライアンドエラーが許されましたが、 今は違います。 トライするのはいいけれども、 エラーは許されないという社会的な風潮があります。
小山:いろいろやってみて、 トラブルが起きたら起きたでその対応でスキルも上がりましたけど、 今はそういうのはもうできないですからね。
▶ 岡山でこれだけ活躍される貴社から見ても、 東京と比べて不利な部分があると実感されているわけですね。
小山:デジタルデバイドもそうですが、 地域格差は確実にありますね。 そもそも、 インターネットとローカライズが相反するという問題もありますが。 まずはIXがある大都市近郊じゃないと速度が出ませんよね。 かといって、 地域IXを作ると今度はトラフィックが少ないという課題が出てきます。
▶ 最近はネットワーク業界では地域NOGなどがたくさん作られて活動が盛り上がっているように見えるのですが、 もっと根本的なところで課題があるということですね。
小山:電力という点で見ても、 関西ですら東京の1/3ぐらいの規模しかありません。 ネットワークについても、 遅延などの問題が解消していくと 「日本の拠点は東京と大阪の2ヶ所あればそれでいいじゃないか」 みたいな方向にいってしまわないか不安に思っています。
最近、中四国地域の地域NOGとしての3SNOGに参加しています。 3Sは山陰、山陽、四国のSです。 今、中国地方で働いている人は、 地域で働くことにアイデンティティを持っている人達です。 そういう人との繋がりを大事にしていきたいと思っています。
次世代の育成のためには単に知識を教えるだけではなく、応用力を身につけさせる教育が絶対に必要
▶ 本日のお話に出てきた課題の中で、JPNICに解決のお手伝いが できるところや、JPNICへ期待するところなどはありますでしょうか。
小山:JPNICは組織として会員数も多く、 その中には地域の会員もたくさんいて、 それらの会員出身の理事も複数います。 そういう意味では、 もっと東京以外の地域の方を向いた活動をしてほしいですね。 D会員には地域の会員が多いですが、 地域が発展して経済が潤えば、 さらに会員が増えるんじゃないでしょうか。 そうすると、それを見た東京の会員も増えるかもしれません。
また、東京への人材流出の話をしましたが、 地域ではスペシャリストの確保が課題です。 現状、当社ではジェネラリストの採用はできていて、 みんな地頭はいいんです。 こういった人材を、スペシャリストとして育成するようなシステムが当社に限らず求められています。 もし教育で解決できるのであれば、 多くの企業の悩みが解決します。 オンライン教育は教育の機会も増えますし便利でいいものではありますが、 それを知識やスキルにするのは本人の力次第という問題があります。 独習でどんどん伸びる人もいますが、 それは元々できる人なんです。 オンラインでは、 学習する様子を見て 「ここはこう考えるといいですよ」 ということが対面のように上手く伝えられません。 また、 教育は他の人と一緒に受けた方が絶対にいい効果が出ると思っています。 負けん気が出るというか、いい刺激になりますから。
あと、 いろいろなものに応用できるメタスキルを伝えられないという問題もあります。 すべてのことについて個別にハードスキルを伝えていると、 到底時間が足りません。 応用力を身につけるには、 やはりオンラインでは限界があると思っています。 例えば、実際にイベントに参加して他社の人と交流すると、 そこでいろいろな考え方に触れたりノウハウを得たり、 他の人の取り組みや頑張りが刺激になったりということがあります。 地方にもないわけではありませんが、 やはり東京に就職した方がそういう機会は圧倒的に多くなります。
こういった地域での交流の場や、 オンラインの課題を解決した教育方法について、 ぜひ取り組んでもらいたいですね。
▶ なるほど、ありがとうございます。 交流の場ということですと、 JPNICではInternet Weekをはじめとした、 普及啓発を目的とした各種イベントを開催しています。 こういった活動について、 何かご意見などはありますでしょうか。
小山:年1回のInternet Weekに加えて、 最近はInternet Weekショーケースを東京以外でもやるようになりましたが、 年2回とかもっと回数が増えるといいなと思います。 もちろん、JPNICは大変になると思いますが(笑)。 先ほども言いましたが、 地域で働いていると他社の人と交流する機会が相対的に少なく、 特に他分野の技術者と一緒に参加できるイベントが少ないんですよ。 そういう意味では、JPNIC単独ではなく、 IPv6関連のイベントと併催するとか、 それ以外でも他のイベントに相乗りするとかでもいいと思います。
またイベントではありませんがIPv6ということでは、 JPNICにはIPv6の推進をもっと進めてほしいですね。 先ほどから話しているように東京と地域にはさまざまな格差があるのですが、 IPアドレスもそうです。 インターネットが普及し出した当初は、 IPv4サイズは比較的大きなサイズで割り当てがされたので、 結果的にどうしても早いうちに申請をした大企業や東京の企業がたくさん持っていて後発の地域企業は不利です。 地域の活性化に繋がるスマートシティの実現にも、 IPv6の普及は必要だと思います。
あとはセキュリティです 。今は何をするにもセキュリティの問題がついてきますので、 会員向けにセキュリティ情報を伝えていくとか、 インシデント対応などの際に力を貸してもらえるとか、 そういうのがあれば嬉しい会員は多いと思いますね。
▶ 本日はいろいろと興味深いお話をたくさん聞くことができました。 ありがとうございます。 最後に伺いたいのですが、「インターネット」とは何でしょうか?
岩﨑:現代社会の基盤となる重要なインフラです。 ネットワーク構築における軽微な不具合、 例えばケーブルの接続不良や設定ミスが、 時に多くの人々に大きな影響を与える可能性があります。 そのため、 その責任の重さを意識しながら日々の業務に取り組んでいます。 社会インフラの一部として貢献できることに大きなやりがいを感じています。
小山:自由ですかね。 Vint Cerf氏が世界中の人を自由にさせるんだと作ったもので、 いい意味でも悪い意味でも自由という概念の象徴だと思います。 最近はインフラになってしまったことでインターネットがインターネットではなくなってしまった面もありますが、 やはり自由であるためには秩序を守る必要があります。 また、インターネットによって情報を発信する力をみんなが持つようになりましたが、 最近はそこに地域差があることを憂慮しています。 都市部以外のトラフィックは下りが8割で上りが2割という感じで、 情報が入るばかりで出ていっていません。 岡山という地でインターネットをやっていくのであれば、 出ていく方を強くしていけば、 経済も強くなるのではと考えています。 一極集中ではなくもっと分散していってほしいし、 分散できるようにしたいですね。
小西:一言で言えば、 無限の可能性と無限の危険性が共存している空間でしょうか。 インターネットには壁は存在せずに自由にやり取りができますが、 隣にいるのはもしかしたらテロリストかもしれません。 素晴らしいものである反面、 そういう危険性もあるということを常に忘れずにいることが大事だと思います。